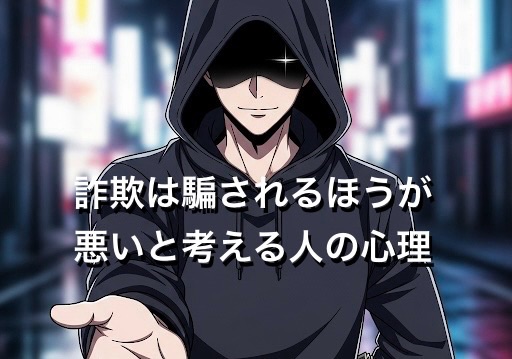詐欺は騙されるほうが悪いと考える人の心理を解説します。
騙すほうが間違いなく悪いのに、なぜ世の中には騙されるほうを責める人がいるのか。
その心理が気になる人は参考にしてみてください。
「騙されるほうが悪い」という言葉に抱く違和感の正体

巧妙化する詐欺事件が後を絶たない中で、しばしば耳にする「騙されるほうにも問題がある」「注意していれば防げたはずだ」という言葉。
悪質な犯罪行為そのものよりも、被害者の落ち度に目が向けられるこの風潮に、釈然としない思いや言葉にしがたい違和感を抱いた経験はないでしょうか。
悪いのは100%人を陥れようとする加害者であるはずなのに、なぜ被害者が非難の対象になることがあるのか。その根深い疑問は、多くの人が一度は感じたことのあるものです。
その違和感の正体は、人間の心に潜む、ある種の「防衛機制」や「思考の癖」にあります。その複雑な心理メカニズムを、一つひとつ丁寧に解き明かしていきましょう。
他人事ではない被害者非難(ヴィクティム・ブレイミング)の構造
「騙されるほうが悪い」という言葉は、より大きな社会問題である「被害者非難(ヴィクティム・ブレイミング)」の典型的な一例です。
被害者非難とは、事件や事故が起きた際に、その原因を加害者や社会構造に求めるのではなく、被害者自身の言動や注意不足に帰着させてしまう考え方を指します。これは詐欺だけでなく、さまざまな犯罪被害において見られる根深い問題です。
誰もが何らかの形で被害者になりうる現代社会において、この思考は被害者をさらに孤立させ、社会全体を危険に晒すことにつながる決して他人事ではない課題なのです。
その言葉の裏にあるのは「自分は大丈夫」と信じたい心の防衛機制
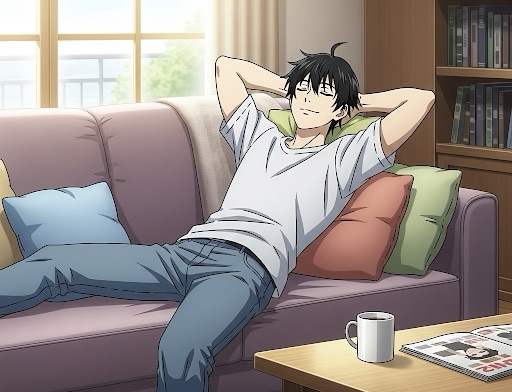
「騙されるほうが悪い」という一見すると冷酷な言葉は、必ずしも発言者の悪意や攻撃性から生まれるわけではありません。
むしろその多くは、発言者自身が予測不能な脅威に満ちた現実から心を守るために無意識に働かせる、「心の防衛機制」の表れなのです。
この言葉は、理不尽な悪意が誰にでも牙をむく可能性を認めたくないという思いから、自分は安全な場所にいると信じ込むための一種の自己暗示といえます。その心理の根幹には主に3つの要素が絡み合っています。
世界は公正であってほしいという無意識の願い
人の心には、「真面目に生きていれば報われ、悪いことをすれば罰せられる」という、因果応報的な秩序だった世界を信じたい根源的な願いがあります。
善良な人が何の前触れもなく財産を奪われる詐欺被害は、この「世界は公正である」という信念を根底から覆す、きわめて不快な出来事です。
そのため、心はこの矛盾を解消しようと、「被害者側に何らかの落ち度があったから悪い結果が起きたのだ」と結論づけます。
そうすることで、「世界はやはり公正だった」と自身の世界観を守り、心の平穏を保とうとするのです。
「自分は違う」という詐欺被害への恐怖から目をそらす心理
詐欺被害のニュースに接したとき、多くの人の心には「次は自分かもしれない」という漠然とした恐怖が芽生えます。この不快な感情を和らげるもっとも簡単な方法が、「被害者と自分を切り離す」ことです。
「あの人は欲深かったからだ」「注意力が散漫だったに違いない」と被害者の個人的な資質に原因を求めることで、「自分は欲深くないし、注意深いから大丈夫だ」という安心感を得ることができます。
これは、詐欺という脅威を直視する恐怖から目をそらし、「自分は被害に遭うはずがない特別な存在だ」と思い込むための無意識の心理的な壁なのです。
詐欺の巧妙さを知らないことによる単純な想像力の欠如
心理的な要因に加え、単純な情報不足や想像力の欠如も被害者非難につながる大きな一因です。
詐欺の中には、個人の心理を巧みに操るだけでなく、複数の人間が役割分担して被害者を追い詰める「劇場型」の組織犯罪もあります。
しかし、「騙されるほうが悪い」と考える人の中には、その巧妙な手口の実態を知らず、昔ながらの単純な詐欺のイメージしか持っていないケースが少なくありません。
自分がそのような状況に置かれたらどうなるか具体的な想像が及ばないため、「自分なら簡単に見破れるはずだ」という、根拠のない万能感に陥りやすいのです。
騙されるほうが悪いと思ってしまう5つの心理メカニズム

「騙されるほうが悪い」と考える背景には、心の防衛機制が存在することを述べました。心理学の世界では、このような心の働きが、誰にでも起こりうる「認知バイアス(思考の偏りや癖)」として、さまざまに研究されています。
これは決して特別な人だけが持つ冷酷な思考ではなく、人間の脳が持つ普遍的な性質の一つです。
被害者非難につながりやすい代表的な5つの心理メカニズムを解説していきましょう。
公正世界仮説:努力は報われて悪い行いは罰せられるという信念の罠
私たちの心の奥底には、「世界は公正な場所であってほしい」という強い願いがあります。これを心理学では「公正世界仮説」と呼びます。
この信念は、日々の努力の動機となったり、社会の秩序を信じる基盤となったりする一方で、理不尽な出来事に直面した際には「罠」として機能します。
善良な市民が一方的に被害に遭う詐欺事件は、「世界は公正ではない」という事実を突きつけます。
この不快な現実を受け入れる代わりに、私たちの心は「被害者側に何か原因があったに違いない」と解釈を変えることで、「やはり世界は公正だった」と物語を完結させようとします。
この認知の歪みが、被害者への非難を生むもっとも根源的なメカニズムです。
正常性バイアス:「自分だけは詐欺に遭わない」という根拠なき確信
「正常性バイアス」とは、予期せぬ異常事態に遭遇した際に、「自分には関係ない」「大したことではない」と事態を過小評価してしまう心の働きです。
災害時に「まだ大丈夫だろう」と避難が遅れるのも、このバイアスが一因とされます。詐欺に関しても同様で、多くの人は「自分だけは騙されない」という根拠のない確信を持っています。
このバイアスが被害者非難として現れるとき、「自分なら、その異常事態に気づけたはずだ」といった過信につながります。
そして、被害者がなぜ気づけなかったのかという点にばかり目が向き、「注意力が足りない」と安易な結論に至ってしまうのです。
自己奉仕バイアス:自分の成功は実力で他人の失敗は自己責任と考える心
「自己奉仕バイアス」とは、物事の原因を自分に都合よく解釈する思考の癖です。例えば、自分が成功したときは「自分の努力や能力のおかげだ」と考え(内的要因)、失敗したときは「運が悪かった」「環境のせいだ」と考える(外的要因)傾向を指します。
このバイアスは、他者を評価する際にも影響を及ぼします。他人が失敗した場合、つまり詐欺に遭った際には、「その人の性格や能力に問題があったからだ(内的要因)」と結論づけやすくなります。
「あの人が欲張ったからだ」「知識がなかったのが悪い」といった非難は、この自己奉仕バイアスが他者に対して働いた典型的な例といえるでしょう。
認知的不協和:被害者の存在が「自分の安全な世界観」を脅かすため被害者を非難して心の平穏を保つ
人は、自分の中に矛盾する二つの考えを同時に持つと、不快な気持ちになります。これを「認知的不協和」と呼び、心はこの不快感を解消しようと無意識に考え方を修正しようとします。
「①私は注意深く安全に暮らしている」という自己認識と、「②私と変わらないはずの普通の人が理不尽な詐欺被害に遭った」という事実は、強い矛盾を生み出します。
この不快な矛盾を解消する手っ取り早い方法が、②の認識を「②被害者は自分とは違う“何か落ち度のある人”だった」と歪めてしまうことです。
こうして被害者を自分とは異なる存在と見なすことで、①の安全な世界観を守り、心の平穏を取り戻すのです。
後知恵バイアス:結果を知ってから「なぜ防げなかったのか」と過去を断罪する思考
「後知恵バイアス」とは、物事の結果が判明したあとに、あたかも最初からすべてを予測できていたかのように感じてしまう心理現象です。
「だから言ったのに」「こうなることは分かっていた」という言葉の背景には、このバイアスが潜んでいます。
詐欺事件の全貌が報道などで明らかになったあとでは、犯人の手口や矛盾点は誰の目にも明白に映りますが、被害者は事件の渦中にあり、断片的な情報しか与えられず、心理的に追い詰められています。
後知恵バイアスは、この被害者が置かれていた当時の困難な状況を忘れさせ、「こんな簡単なことになぜ気づかなかったのか」と、現在の安全な視点から過去を不当に断罪させてしまうのです。
なぜ「騙す側」ではなく「騙される側」に目が向いてしまうのか?
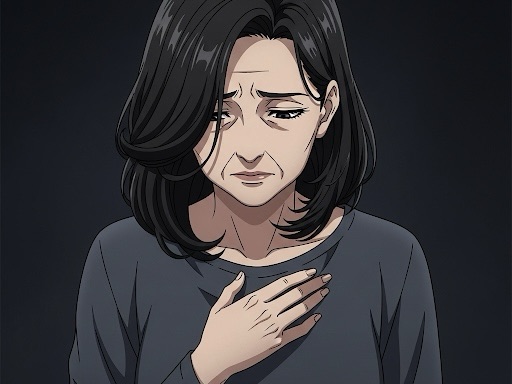
前述した個人の心理バイアスは、被害者非難が生まれる大きな要因ですが、それだけでは、なぜ私たちの社会でこれほどまでに「騙される側」の言動が注目され、時に非難の対象となってしまうのかをすべて説明することはできません。
実は、私たちの思考を無意識のうちに被害者側へと誘導する、より大きな社会的・構造的な要因が存在します。
個人の心の問題だけでなく、社会が作り出す空気そのものが、加害者よりも被害者に目を向けさせているのです。
巧妙化・劇場化する詐欺の手口!「注意すれば防げる」はもはや幻想
多くの人が抱く詐欺のイメージは、実際の犯行手口から大きくかけ離れているのが現実です。現代の詐欺は、単なる個人の嘘や思いつきではなく、周到な脚本と役割分担に基づいて実行される高度に組織化された「劇場型犯罪」へと進化しています。
警察官や銀行員、弁護士など、社会的に信頼性の高い役職を複数の犯人が演じ分け、被害者を巧みに信用させ、冷静な判断力を奪っていきます。
このような状況下では、「少し考えればおかしいと気づくはず」という個人の注意喚起は、もはやほとんど意味をなしません。
しかし、こうした犯罪の巧妙な実態が十分に知られていないため、多くの人々は依然として「注意さえすれば防げる」という古い前提に立っています。
この情報格差こそが、被害者の状況への想像力を欠如させ、「なぜ防げなかったのか」という安易な非難を生む温床となっているのです。
メディア報道の影響:被害者の落ち度が強調されやすい構造
テレビや新聞などのメディアが詐欺事件を報じる際、その報道のフレームも私たちの視線に影響を与えます。
ニュースは視聴者への「教訓」や「注意喚起」を意図するため、どうしても「どのような手口で騙されたのか」「被害者はなぜ信じてしまったのか」という点に焦点が当たりがちです。
その結果、報道側の意図とは裏腹に、受け手には被害者の行動の「おかしさ」や「脇の甘さ」といった部分が強く印象付けられてしまうことがあります。
また、匿名で実態が掴みにくい加害者集団に比べ、被害者の状況はある程度具体的に報じることが可能です。
結果として、ストーリーの中心が被害者側に偏り、その一挙手一投足が分析・評価の対象にされやすくなるという構造的な問題が存在します。
自己責任論が強い社会全体の風潮
よりマクロな視点として、社会に根強く存在する「自己責任論」の風潮も無視できません。
この考え方は、個人の自立を促す正の側面を持つ一方で、何らかの困難に直面した人々を「本人の努力や注意が足りなかったからだ」として切り捨て、社会全体で支える視点を弱めてしまう負の側面も持ち合わせています。
詐欺被害もこの自己責任論の文脈で語られやすく、「自分の財産は自分で守るのが当然」「うまい話に乗る方が悪い」といった論調が、被害者を救済する声よりも先に立ちがちです。
社会的なセーフティネットの重要性よりも個人の責任を厳しく問う社会の空気が、被害者を非難し、孤立させる土壌を育んでいるといえるでしょう。
騙されるほうが悪いという考え方がもたらす3つの深刻なリスク

騙されるほうが悪いという考え方は、単に被害者の心を傷つける倫理的な問題にとどまりません。それは、社会の安全基盤を静かに蝕み、測定可能な悪影響を及ぼす具体的な「リスク」です。
この思考が蔓延することは、意図せずして犯罪が起きやすい社会を形成することに加担してしまいます。
被害者非難という考え方がもたらす、連鎖的で深刻な3つのリスクについて解説していきましょう。
被害者を孤立させて相談できない状況に追い込む(二次被害)
もっとも直接的で深刻なリスクは、被害者本人に与える影響です。詐欺の被害に遭った人は、大切な財産を失った経済的ショックに加え、「なぜあんな嘘を見抜けなかったのか」という激しい自責の念に苛まれています。
そのような精神的に追い詰められた状態で、周囲から「騙されるほうが悪い」と非難を浴びることは、傷口に塩を塗り込むような行為にほかなりません。
これは「二次被害」と呼ばれ、被害者をさらに深く傷つけます。この二次被害への恐怖から、被害者は家族や友人、さらには警察にさえ被害の事実を打ち明けることをためらうようになります。
結果として、誰にも相談できずに一人で苦しみを抱え込み、精神的に孤立し、必要な支援や救済措置から遠ざかってしまうのです。
詐欺事件の潜在化を招き犯罪者集団を利する結果になる
被害者が相談や被害届の提出をためらうようになると、その事件は公的な記録に残らず、警察もその発生を認知できない「潜在化」という状態に陥ります。
事件が潜在化することは、社会にとって計り知れない損失です。警察は犯罪グループの実態や最新の手口を正確に把握できなくなり、効果的な捜査や対策を講じることが困難になります。
また、新たな手口の情報が社会で共有されないため、類似の被害が次々と発生するのを防ぐことができません。
最終的に、この状況は犯罪者集団にとって、きわめて都合の良い活動環境を提供することになります。
「被害者が声を上げにくい社会」は、詐欺師たちにとってリスクの低い安全な狩場となり、被害者非難の風潮が結果的に彼らの犯罪行為を利することにつながってしまうのです。
社会全体の危機意識を低下させて詐欺への脆弱性を高める
被害者非難の考え方が社会に広まることは、長期的に社会全体の危機意識を麻痺させることにつながります。
「騙されるのは一部の注意力が足りない人や欲深い人だ」という認識が定着すると、「自分は注意深いから大丈夫」と考える人が増え、社会全体の詐欺に対する警戒レベルが低下します。
詐欺という問題を「個人の資質の問題」として矮小化してしまうと、金融機関のシステム改善や法整備、地域社会での見守り体制の強化といった、社会全体で取り組むべき本質的な対策への機運が削がれてしまいます。
個人の責任を過度に追及する風潮は、社会全体の防御力を低下させ、結果として、より巧妙化する詐欺犯罪に対する「脆弱性」を高めてしまう深刻なジレンマを生むのです。
その思考から脱却するために今日からできること

この考え方が誰の心にも潜む認知バイアスや社会的な影響によって形作られる無意識の産物である以上、意識的な努力によってその思考の罠から抜け出すことは十分に可能です。
それは、特別な誰かになることではなく、自分自身の心の働きを少し客観視し、知識と思いやりの視点を加えるという、ささやかでも重要な一歩から始まります。そのための具体的な3つの方法をご紹介しましょう。
まずは自分の認知バイアスを自覚する
思考や行動を変えるための第一歩は、自分自身の状態を客観的に認識する「メタ認知」から始まります。
この記事で解説した「公正世界仮説」や「後知恵バイアス」といった思考の癖が、自分自身の心の中にも存在しうるという可能性を認めることが重要です。
例えば、詐欺事件の報道に触れて「なぜこんなことに」と被害者の行動に疑問を感じた瞬間に、「待てよ、これは結果を知っているから言える後知恵バイアスではないか」と一歩立ち止まって考えてみる。
完璧にバイアスを消し去ることは難しくても、その存在を自覚し、自分の思考に疑いの目を向けるだけで、自動的に被害者を非難してしまう思考回路にブレーキをかけることができます。
最新の詐欺手口を知り「誰でも被害に遭う可能性」を理解する
被害者非難の一因である「想像力の欠如」は、正しい情報を得ることで克服できます。警察庁や国民生活センターといった公的機関は、実際に報告された最新の詐欺手口について常に情報発信を行っています。
これらの信頼できる情報源に定期的に触れ、現代の詐欺がいかに組織的で巧妙であるかを具体的に知ることが大切です。
巧妙な偽サイトに誘導するフィッシング詐欺や、パソコン画面に警告を出して不安を煽るサポート詐欺など、その手口を知れば知るほど、「自分なら絶対に見抜ける」という過信が、「自分も同じ状況なら騙されたかもしれない」という現実的な認識へと変わっていきます。
知識は、根拠のない万能感を打ち砕き、他者の状況を正しく理解するための不可欠な土台となるのです。
被害に遭った人の話に耳を傾けてその痛みと状況を想像する
知識による理解をさらに深めるのが共感による理解です。被害に遭った人を、単なるニュースの中の登場人物や教訓のための「失敗例」として見るのではなく、自分と同じように日々の生活を営む一人の人間として捉え直すことが求められます。
被害者の手記やインタビュー記事を読んだり、ドキュメンタリー番組を視聴したりすることで、そこにある後悔や恐怖、絶望、そして家族への申し訳なさといった生々しい感情に触れることができます。
その痛みを少しでも想像することができたとき、「騙されるほうが悪い」という言葉がいかに無神経で残酷なものであるかを理屈ではなく心で理解できるはずです。
他者の痛みを想像する力こそが、無自覚な非難の言葉を思いやりのある態度へと転換させる原動力となります。
もし身近な人が被害に遭ったら知っておきたい正しい寄り添い方

詐欺被害は、もはやテレビの中だけの出来事ではありません。いつ、自分の大切な家族や友人がその当事者になるかわからないのが現代社会の現実です。
もし、そのような事態が起きてしまったとき、身近な存在である人の最初の対応が、被害に遭った方のその後の回復プロセスにきわめて大きな影響を与えます。
被害者の心をさらに傷つけることなく、その立ち直りを支えるための具体的で正しい関わり方について解説していきましょう。
やってはいけないNG言動:「なぜ騙されたの?」と責めること
身近な人が被害に遭ったと知ったとき、驚きのあまり「なぜそんなことに?」「どうして気づかなかったの?」と原因を問いただしたくなるかもしれません。
しかし、これらの言葉は、たとえ事実を知りたい純粋な意図から発せられたとしても、被害者にとっては「あなたの判断は愚かだった」という厳しい非難のメッセージとして突き刺さります。
被害者は、誰よりも自分自身を「なぜ騙されたのか」と激しく責め、後悔の念に苛まれています。その傷口に追い打ちをかけるような詰問は、被害者の心を完全に閉ざさせ、深刻な二次被害を生むだけです。
「私だったら騙されない」「もっと慎重になるべきだった」といった、比較や安易な説教も同様に避けるべき言動です。
寄り添う姿勢:「大変だったね」と気持ちを受け止めて味方であることを伝える
被害者にとって今もっとも必要なのは、原因追及やアドバイスではなく、傷ついた感情をそのまま受け止めてもらうことです。
まずは、「大変だったね」「つらかったでしょう」といった言葉で、その苦労をねぎらいましょう。そして、勇気を出して打ち明けてくれたことに対し、「話してくれてありがとう」と感謝を伝えます。
これらの言葉は、被害者の抱える罪悪感を和らげ、話しても大丈夫だという安心感を与えます。
そのうえで、「何があっても自分はあなたの味方だ」「一人で抱え込まないでほしい」と、決して孤立していないことを明確に伝えることが重要です。
この揺るぎない安心感こそが、被害者が混乱から抜け出し、次のステップへと進むための土台となるのです。
具体的な行動を支援する:公的な相談窓口へつなぐ
精神的なサポートと並行して、具体的な行動を支援することも大切です。ただし、家族や友人が独自に犯人側と連絡を取ったり、解決しようと動いたりするのは大変危険です。
身近な人ができるもっとも建設的で安全な支援とは、被害者を専門的な知識を持つ「公的な相談窓口」へとつなぐことです。
どこに相談すればよいかわからない場合は、まず警察相談専用電話である「#9110」に電話することで、状況に応じたアドバイスや担当窓口の案内を受けられます。
また、契約トラブルなどが関わる場合は、消費者庁の「消費者ホットライン(188)」も有効です。
本人が混乱して行動できない場合は、「一緒に電話してみようか?」と声をかけ、相談への心理的なハードルを下げてあげることも重要な支援となります。
まとめ:その言葉は社会を蝕む刃!必要なのは非難ではなく理解と支援

「騙されるほうが悪い」という言葉の裏に潜む、複雑な心理メカニズムと社会的な構造を解き明かしてきましたが、それは心の平穏を保ちたい無意識の防衛機制や、誰の心にも存在する認知バイアス、そして社会に根付く自己責任論の風潮などが絡み合って生まれる根深い現象です。
しかし、その背景がいかなるものであれ、この言葉がもたらす結末はきわめて深刻です。被害者を二次被害で苦しめ、孤立させ、事件の潜在化を招くことで、結果的に犯罪者が活動しやすい社会を形成してしまいます。その言葉は、意図せずして社会の安全網を切り裂く静かで鋭い刃となりうるのです。
この問題に対して、私たちは明確な結論を持つべきです。すなわち、悪いのは100%人の弱さや信頼につけ込み、人生を破壊しようとする「騙す側」であり、そこに議論の余地は一切ありません。
私たちが向けるべきエネルギーは、被害者への非難ではなく、その心の痛みを理解しようと努める想像力と、具体的な支援へとつなげる行動です。
まずは、自分自身の心に潜むバイアスを自覚すること。そして、巧妙化する詐欺の現実について正しい知識を身につけること。そのうえで、もし身近な人が被害に遭った際には、温かい言葉で寄り添い、専門的な窓口へとつなぐ手助けをすること。
一人ひとりのその小さな意識の変化こそが、被害者が声を上げやすい社会、そして犯罪者が成功しにくい社会を築くための確実で大きな一歩となるのです。